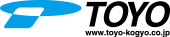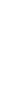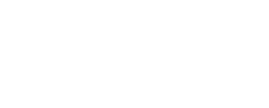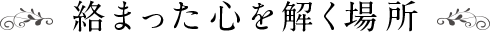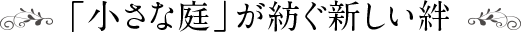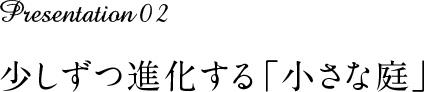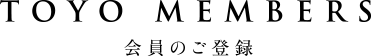キャンバスが絵を描くためにあるように、庭はそれぞれの暮らしを描くためにあります。
雑誌や旅先で見かけた理想の庭を形にするのはもちろん、忘れることのない記憶の中の印象的な草木を取り入れることもできます。
この物語で言えば、庭の一本のシンボルツリーを目にするたびに、父と母は若かりし日のほのかな恋心や大切に紡いできた愛情を思い出すでしょう。
いつの日か、この庭を形づくった日々を思い出すためにも、庭は存在していくでしょう。
もちろん健斗のように、将来の夢を反映することだってできます。
そして、いつか遠い未来に振り返った時には、この庭から夢がはじまったことも鮮やかな記憶としてよみがえるはずです。
これからお届けするのは、「小さな庭」にまつわるある家族の物語。
夢や理想が一人ひとり違うように、庭のある暮らしがもたらすものも家族それぞれで違います。
小さな庭と、そこで感じる幸せな時間。家族の風景を覗いてみましょう。

夫の父が創業した小さな洋菓子店は、私たちの代になってカフェを併設したころから雑誌によく取り上げられるようになった。
「ね、ここのカフェって、お花も素敵なのよ」「ホントだ!」
お客様の話し声が飛び込んでくる。
店のハッシュタグが付いたSNS投稿には最近スイーツとともに店内の花がアップされることが増えてきた。
大学で設計を学びながら、花屋でバイトをしている息子が生けたものだ。
私の横でケーキを並べていた夫が、まるで自分が褒められたように照れたような顔をしてキッチンへと戻っていく。
「ほんと、子どもみたい」吹き出しそうなのをこらえる。
夫と息子は、本当にそっくりだ。
高校生になったころから、息子はほとんど口を利かなくなった。
「お店は継がないよ、もっと違う仕事をしたいんだ」
息子の夢を聞いたときに、夫がへそを曲げたのがきっかけだ。
もはや修復不可能にも見える夫と息子の冷戦状態を横目に朝の支度を済ませるのにも慣れはじめていた。
「ほんっと、そっくりなんだから!」
黙ったままふてくされる夫はまるで子どもみたいだ。
「仕方ないでしょう?言い出したら聞かないのはあなたとおんなじ」
笑いながら、さて、なだめるにはどうしたものか、と作戦を考えるのは付き合い始めた大学時代からまったく変わらない。
そんな折、お店のテラスの改装計画が持ち上がった。
せっかくなら大学時代の友人であるガーデンデザイナーの美保にお願いして、自宅のお庭にも手を入れましょう、と提案したのは私だ。
打合せ当日、母の厳命から逃れられず立ち会っていた息子に美保が話しかける。
「君さ、ガーデン設計には興味がない?ちょっと人手が足りないのよ」
「えっ!」息子と夫が同時に声を上げる。こんなところまでそっくり。
そして照れくさそうな顔で息子はその申し出を引き受けたのだった。
それから1か月も経ったころだっただろうか。
「ちょっと見てほしい」と息子がちょっと照れたように大きなスケッチブックを持って、リビングに降りてきた。
そこに描かれていたのは、驚くほど細密なガーデンの設計図だった。
「父さん。僕に庭をつくらせてほしい」
息子は夫の目をまっすぐに見て、そして頭を下げた。
ガーデンが完成したのは、よく晴れた秋の日だった。
「健斗、よく頑張ってるわよ」と美保からたびたび報告を受けてはいたものの、実際に目にするまでは気が気じゃなかった。
庭を正面から見てほしいという息子の意向で店から出て、ぐるっと自宅の玄関へと回る。
一足先に庭を見た夫が立ち止まった。視線の先にアカシアの葉が揺れている。
夫が照れたような顔で息子の目を見つめる。
「昔、アカシアの木の下でプロポーズしたって聞いたから…」
息子がちょっと勝ち誇ったようにそういった。


「健斗君は小さいころ、何になりたかったの?」
まるで小動物のような目で、じっと僕を見つめながら彼女が聞く。
「実は何にも夢がなくて…。でもこの庭が目標をくれたんだ」
父と僕を和解させようと母とその友人が立てた作戦に僕らはまんまと乗っかってしまったのだということを手短に説明する。
「それ、運命だったんだよ!だって今の道につながったんだから」
弾むような声。彼女の言葉はなぜかいつも僕に力をくれた。
パティシエになる夢のために父のもとで修業していた2つ上の彼女に僕が惹かれるのに時間はかからなかった。
なのに毎日話すようになったころ、彼女が留学することを知った。
「パリへはいつ?」「来月」「そっか、帰るのはいつ?」「わかんない」
結局、僕らは彼女が旅立つ日まで、あいまいな関係のままだった。
大学卒業後に、建築とガーデン設計を学ぶためにとフランス留学を決めたのは彼女がパリにいる、というのも密かな理由だった。
ただ、パティシエを目指す彼女の忙しそうな姿に気後れし最初は週末ごとに案内してもらっていたものの、パリに慣れたころから、だんだん連絡を取らなくなってしまった。
そして、いつの間にかガーデンデザインの面白さに目覚め、気がつくと日本へ帰ってきたのは実に3年ぶりだ。

「なんで、もっと連絡しなかったんだろうなぁ」
そんなことを思いながら見慣れた駅で降り、見慣れたカフェに着いた。
「ただいま」とドアを開けると…こんなことって!
なんと顔を出したのは、今しがたまで思い出していた彼女だった。
「新しいショコラティエだ」と父に紹介される。
父は、ちょっと勝ち誇ったような顔をして「母さん、庭のほうにいるから」といった。
動揺を隠すために、いったん店を出て、玄関に向かう。
どうやら庭は母がきちんと手入れをしているようだ。
「どう?なかなか素敵な庭になったでしょ?」
アガパンサスの茂みの中から母の声がする。
「だけど、なんだかもの足りないだろう」
いつの間にか後ろにいた父がつぶやく。
「確かに少し寂しいかも。手直しが必要だね」と僕。
「まったくもう。うちの男どもは!!ねぇ!」と母が呆れたようにいう。
振り返ると、彼女がどこか母に似たあっけらかんとした表情で
「だったら何度でもつくりなおせばいいじゃない?」と笑っていた。
アカシアの葉が揺れている。
庭も、そして一度は手を離してしまった絆も、この庭からまた紡いでいこう。
そう誓う僕を、シンボルツリーらしく育ったアカシアの木が見守っている。
年を重ねていくと、家族構成やライフスタイル、そして好みも少しずつ変わっていくもの。
また、木々の成長とともに全体の配置も変えることが必要になる場合もあります。時代によって流行は移り変わるため、その時々の自分たちの暮らしに合わせて、カスタマイズしていくのもいいでしょう。
庭は、人生や人との絆と同じ。一度完成させれば、おしまいではありません。
整えたり、調和させたり、合わせたり。そうやって手をいれていく。
そのときどきで最良でありつつも終わりがない、だからこそ、いつまでも楽しめるのだと考えることもできそうです。